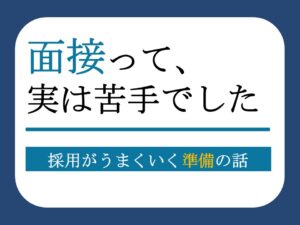建設業の働き方改革|年間休日120日を実現する方法とは?
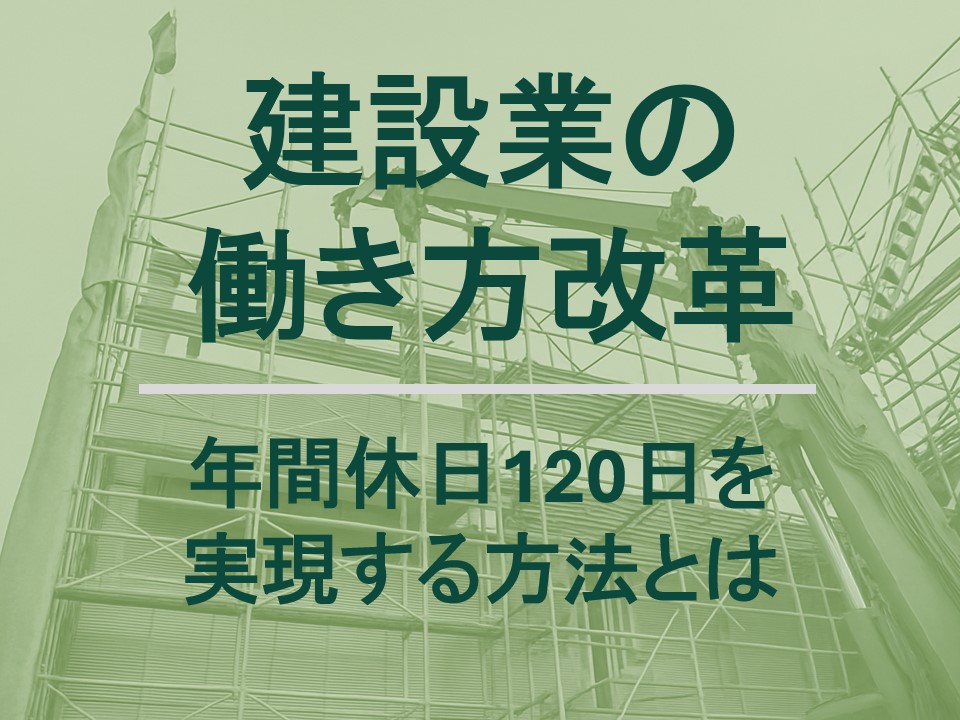
「建設業に休みなんてない」…それ、本当ですか?
「建設業に休みなんてない」
そんな声が聞こえてきたのは、リフォーム専門のクライアントB社を訪問した日のこと。
こんにちは。社長の右腕、人事チーム代表の押元です。
採用のために「もっと休みを増やすことも視野に」とお話しした私に、現場の責任者はこう言いました。
「ウチは年間休日90日。これ以上休めって言われてもムリですよ」
お気持ち、よくわかります。
現場は人手不足。天候にも左右されるし、納期はギリギリ。
それでも――「人が辞める」「人が来ない」という課題を前にして、“今までの当たり前”を見直さざるを得ない瞬間が、確かにやってきています。
建設業で年間休日120日を目指す理由
「休日が多い」=「働き方改革」ではない
そもそも、なぜ年間休日120日が話題になるのでしょうか?
それは、
転職サイトに掲載できる最低ラインになっているから
若手が求める労働環境の基準だから
「休める会社」=「安心して働ける会社」という印象づくりになるから
つまり、求人応募数を増やすための条件の一つなんです。
でも、休日数だけを増やすのは本質ではありません。
重要なのは、「どうやって休める体制をつくるか」――です。
年間休日120日を実現した企業のリアル
B社で、はじめて「年間休日120日」を導入するにあたって、こんな課題に直面しました。
「休ませたいけど、現場が回らない」
そのとき私が提案したのは、次の3つです。
✅ 1. 完全予約制に移行し、現場の計画施工が可能に
まず取り組んだのは、「突発の仕事が多すぎて休めない」という状態を変えること。
そこで、完全予約制への移行を提案しました。
着工や引き渡し日を前もってしっかり調整しておくことで、急な依頼や無理なスケジュールを減らせるように。
さらに、前年度末に「休業日カレンダー」を作成し、協力会社や施主にも事前に共有。
結果的に、施工の予定が立てやすくなり、「この日はみんなで休もう」という計画が現実味を帯びてきました。
✅ 2. 繁忙期(3〜5月)以外は月10日休み
次に手を入れたのが、「休みたいけど人手が足りない」という構造。
ここでは、多能工化とチーム制の導入を進めました。
要は、「○○さんがいないと仕事が止まる」状況をなくすということ。
業務の分担や引き継ぎを仕組みに落とし込み、繁忙期をのぞけば月10日の休みが取れるように設計。
シフト制や交代制も取り入れながら、無理のない週休2日体制に近づけていきました。
✅ 3. 年間休日:90日 → 120日に
そして最終的には、年間休日90日から120日へ。
もちろん、一気に変えたわけではありません。
まずは、設計や事務などの内勤部門から先に改革。
そのうえで、現場も協力会社や外注パートナーとの連携を強化し、「代わりに現場に出られる人」を確保する体制をつくっていきました。
また、元請や発注者との調整を通じて、工期に余裕を持たせる交渉も行いました。
こうした地道な積み重ねが、「本当に120日休める会社」へとつながっていったんです。
「休みを増やしたら、売上が下がるのでは?」という不安に向き合う
ここまで読んでいただいた方の中には、こんな疑問が浮かんでいるかもしれません。
「休みを増やすって、売上はどうなるの?」
「粗利が落ちたら意味がないのでは?」
そのお気持ち、よくわかります。
実際、B社でも「休日を120日に増やす」と決めたとき、一番に心配されたのはこの部分でした。
そこで、あらためてお伝えしたいのは――
結論から言うと、短期的には一時的な影響が出るかもしれません。
でも、中長期的にはプラスに転じるケースがほとんどです。
▼短期的には、たしかに“揺れ”はあります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売上への影響 | ・稼働日が減る分、1人あたりの施工量が一時的にダウン ・受注件数や対応件数が絞られる可能性あり |
| 粗利への影響 | ・人件費は固定費なので「休んでも給料」は発生 ・休日分の前倒し施工や工程調整コストが出ることも |
| 業務負荷の集中 | ・休みの分、1日ごとの作業密度が濃くなりがち ・その結果、品質や納期リスクが一時的に高まる可能性も |
だからこそ、単に「休日を増やそう」ではなく、仕組みごと見直すことが必要なんです。
▼中長期では、明らかに“プラスの循環”が生まれます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離職率の低下 | ・休日が増えると、従業員満足・定着率が向上 → 採用・教育コストが減り、粗利率が改善 |
| 生産性の向上 | ・疲れにくくなり、施工ミスや判断ミスが減少 → 再工事やクレームが減り、利益率アップ |
| 採用力の向上 | ・「休める会社」が求人で注目され、若手の応募が増加 → 人手不足が解消し、受注機会の損失も減少 |
| 顧客満足の向上 | ・工程が安定することで、対応品質が一定に → リピートや紹介の受注が増える |
| 工数の標準化 | ・属人化や突発対応が減り、作業の可視化が進む → 無駄・ムラ・ムリの削減で利益構造が安定 |
休みを増やすことで「現場がピリッと引き締まった」という声も、実際にB社から上がっています。
▼粗利を守るために、必要な“4つの視点”
休日を「仕組み」として設計する
→「1日長く働くから1日休める」ではなく、無駄な段取りや待機時間を減らして休む。工程・予実管理を徹底する
→ 工期超過による追加原価を防ぐ体制を、現場単位で設計。受注の質を見直す
→ 手離れが悪く、単価の低い案件は見直し。粗利率の高い仕事へシフト。“1人あたりの粗利”をKPIに置く
→ 売上ではなく、生産性・効率で見る体質に変えていく。
▼まとめ:休日を「増やす投資」と捉えるか、「減らすリスク」と捉えるか
| 観点 | 短期的 | 中長期的 |
|---|---|---|
| 売上 | △(稼働時間減) | ○(採用力&生産性向上) |
| 粗利 | △(固定費率アップ) | ◎(離職減・再工事減・管理精度向上) |
「休日を減らさずに、どうやって売上・粗利を守るか?」
この問いに向き合える会社は、5年後に確実に“勝っている”と、私たちは信じています。
ご希望があれば、御社の業種・人員構成・受注内容に合わせた設計もご一緒に考えます。
「休める体制をつくること」=「経営の筋肉を鍛えること」。そんな視点で、一歩踏み出してみませんか?
まとめ|“ムリ”に見えても、道はある
年間休日120日。
かつての建設業では「非現実的」だったかもしれません。
でも今、現実にそれを実現している会社が、確かにあります。
あなたの会社にも、その道はきっとあります。
「どうせ無理」とあきらめる前に、“変える”ことから逃げない仲間と、話してみませんか?
お問い合わせはこちら!
採⽤から早期戦⼒化までの代⾏サービスに
ご興味がある⽅は無料で相談承ります。
採⽤から早期戦⼒化までの
代⾏サービスにご興味がある⽅は
無料で相談承ります。